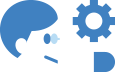2023.12.08MEDISO:インタビュー
認定VCインタビュー 東京大学エッジキャピタルパートナーズ・宇佐美 篤様 塩原 梓様

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の「認定VC(ベンチャーキャピタル)」シリーズ、今回は東京大学エッジキャピタルパートナーズ(以下、UTEC)の取締役/パートナーの宇佐美篤様、プリンシパルの塩原梓様にUTECでの取組と日本のライフサイエンスベンチャー業界について語って頂きました。
|
社名
|
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ
|
|
所在地
|
東京都文京区本郷7丁目3番1号
東京大学南研究棟(アントレプレナーラボ)3F |
|
設立
|
2004年
|
|
ファンド実績
|
■UTEC1号投資事業有限責任組合
・設立年:2004年 ・ファンド総額:83億円 ■UTEC2号投資事業有限責任組合 ・設立年:2009年 ・ファンド総額:71.5億円 ■UTEC3号投資事業有限責任組合 ・設立年:2013年 ・ファンド総額:145.7億円 ■UTEC4号投資事業有限責任組合 ・設立年:2018年 ・ファンド総額:243.1億円 ■UTEC5号投資事業有限責任組合 ・設立年:2021年 ・ファンド総額:304.1億円 |
まずはお二人のご略歴を教えてください

(宇佐美氏)東京大学大学院で薬学を学びPh.D.を取得しました。大学院生のときに、東京大学医学部附属病院とUTECでインターン機会をいただきました。前者では技術に基づく医療の在り方や実臨床の場に新しい医療製品・サービスが導入される過程を知り、研究現場と社会のつながりを意識するようになりました。後者では研究から社会実装までのエコシステムを体感することができました。その後三菱総合研究所に入社して医療をはじめとしたものづくり系のコンサルティング業務を経験し、2013年にUTECに参画しました。
(塩原氏)私も東京大学で薬学を学んでいました。当時は技術の社会実装に興味を持っていたため、大学院修了後にアーサー・ディ・リトルに入社してライフサイエンス領域を中心とした研究開発や戦略立案に携わりました。そこで特にライフサイエンスに関するイノベーションの社会実装は日本だけにとどまっていては難しいと感じ、海外での経験を積むためにロンドン・ビジネス・スクールでMBAを取得しました。ロンドンで学んでいた時期にUTECでインターンをさせていただいたこともあり2021年に参画し、現在は主にライフサイエンス領域のベンチャーへの投資や海外展開の支援を行っています。
UTECの特徴や強みを教えてください
(宇佐美氏)東京大学に軸足を置いて活動していますが、グローバルに展開している点が特徴です。例えば最近では、米国モデルナとのM&Aがなされたオリシロジェノミクスという立教大学発のバイオベンチャーや、欧州ライフサイエンスメーカ大手のユーロフィンとのM&Aがなされたレパトアジェネシスといった企業の提携活動等を支援してきました。また数年前より「ベンチャーパートナー制度」を導入し、研究開発・臨床開発・事業開発、ファイナンスなど、ベンチャーに必要な知識やスキルを提供できる国内外のプロフェッショナル人材を派遣してサポートする取り組みも実施しています。経験豊富なベンチャーパートナーと協業する中でディールに至っています。
(塩原氏)ライフサイエンス領域のベンチャーにとって、特定の分野の高い専門性を持つプロフェッショナル人材にアクセスすることが重要ですが、高い専門性を持ちかつ機動的にスタートアップとの協働ができる方は国内では希少で、国内のベンチャー企業ではアクセスしにくいです。弊社の行っているベンチャーパートナー制度を通じて国内外の適切な専門家の方とお繋ぎすることが、ベンチャー企業の加速度的な成長に繋がっていると実感しています。
(宇佐美氏)エクスパンションステージやレイターステージの企業も支援していますが、シード・アーリー期のベンチャー企業の支援をメインとしている点も当社の特徴です。スタートアップのカンパニークリエーションにも取り組んでおり、オリシロジェノミクスやレパトアジェネシスも、創業の数か月から数年前から、創業科学者の方とやり取りを行うことで、共同創業に至っています。
日本の医療系ベンチャー業界やVC業界には、この10年でどのような変化が生じていると見ていますか
(宇佐美氏)国内の資金調達額が10年前から比べて10倍になったことが挙げられます。2013年は800〜900億円ほどでしたが、現在では9000億円ほどに到達しています。ライフサイエンスだけに限った数字ではありませんが、グローバルではベンチャー企業の総資金調達額が直近では減少していたため、その中で日本における資金調達額が堅調に伸びていることは評価すべき点でしょう。数自体は少ないものの、着実に成功事例も出てきています。オリシロジェノミクス等の事例に加えて、10年という括りには入らないですが、オプジーボ、エンハーツという画期的な医薬品の開発や、独自の創薬開発を行うペプチドリームの躍進などはその際たる例です。日本にも誇れるものはしっかりとあることはポジティブに捉えて良いと考えます。
(塩原氏)特にこの1年で、海外投資家や海外製薬企業から日本での活動について相談いただく機会が急増しました。宇佐美が挙げたような日本の製薬・バイオ分野での成功事例が増えてきていること、高い専門性を持つ人材のベンチャーへの参画が進んでいることなど要因は幾つかあるでしょうが、日本が投資対象として注目を集めていると言えるのではないでしょうか。
その一方で、日本の医療系ベンチャーやVCが克服していくべきことは何でしょうか

(宇佐美氏)成功事例は増えていると言いましたが、それでも先端技術に基づいて研究成果を生み出し、それを製品化、事業化に結びつけるという成功体験を持った方はまだまだ少ないのも事実です。売上を作るのではなく、また基礎研究と製品開発は別物であるとの認識のもと、「こういうデータが出れば製品開発上、価値の訴求ができ、事業化ができる」という開発上のインフレクションポイントを見定められる人材が重要です。こうした人材が少ないのは、日本ではM&Aが圧倒的に少ないからだと考えています。M&Aを経験すると次のチャレンジに進めます。IPOのみではなかなかそうはいきません。米国ではIPOしたバイオベンチャーがM&Aされるケースも多いですが、日本ではまだそのような事例が少ない点も、現状の人材不足に繋がっていると思います。ただし、人材が育つ土壌はこの10年で出来上がってきていますので、次の10年で日本でも専門性を有する海外の機関投資家や製薬企業から評価されるような会社がM&Aされる事例も増加していくことでしょう。そうすれば人材面でも流動性が生じてくるはずです。
日本の医療系ベンチャー業界活性化のために施策を提案するとしたらどのような案が考えられますか
(塩原氏)明治の日本では様々な知識や技術を持った外国人を欧米から招く画期的な制度がありました。当時の国家予算の3分の2ほどを掛けて国内では得難い経験や知識を持つ人々を欧米から招いたことで日本の近代化が進みましたが、現代の日本でもその施策からの示唆を活かせるのではないかと考えています。現在のグローバルのトップクラスの人材は給与水準が高いですが、経験や知識が低い人を5,6人雇うよりも高いレベルの方を1人雇う方が結果的にバリューは高くなります。当社のベンチャーパートナー制度で協力いただいている人々は、「日本にはワールドクラスのサイエンスがある」と感じていただけているからこそ協力いただけていることを実感しており、グローバルのトップクラスの人材にもっと関与いただける可能性は十分にあると思います。ただ、そうした人材を日本のベンチャーが迎え入れるのはコスト面から一般的には難しい面もあるため、経験豊富なグローバル人材の雇用や参画を国が支援することで日本発のベンチャー企業の成長を導けるでしょう。
(宇佐美氏)日本で閉じる「All Japan」精神から脱却することが重要かもしれません。先進的な技術・人材・英知を活かし合い、日本から世界へ向けて発信し、そして世界から日本へと集う「From Japan」「To Japan」を掲げるべきだと考えています。グローバルで見ても画期的な開発支援のプッシュ・インセンティブ、プル・インセンティブの仕組みを整えることで、さらなる世界からの投資を呼び込むこともできるでしょう。他国の周回遅れの後追いとなることは避ける必要があります。次の数年、数十年先を見越して、日本が世界の先駆けとなるような仕組みのもと開発や投資を行っていくことで、企業も人材も日本に集い、それと同時に、世界へと展開していく状況が作り出せるのかもしれません。
(取材者:三菱総合研究所 森卓也・太宰結)
 「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト
「医療系ベンチャー・トータルサポート事業」の総合ポータルサイト